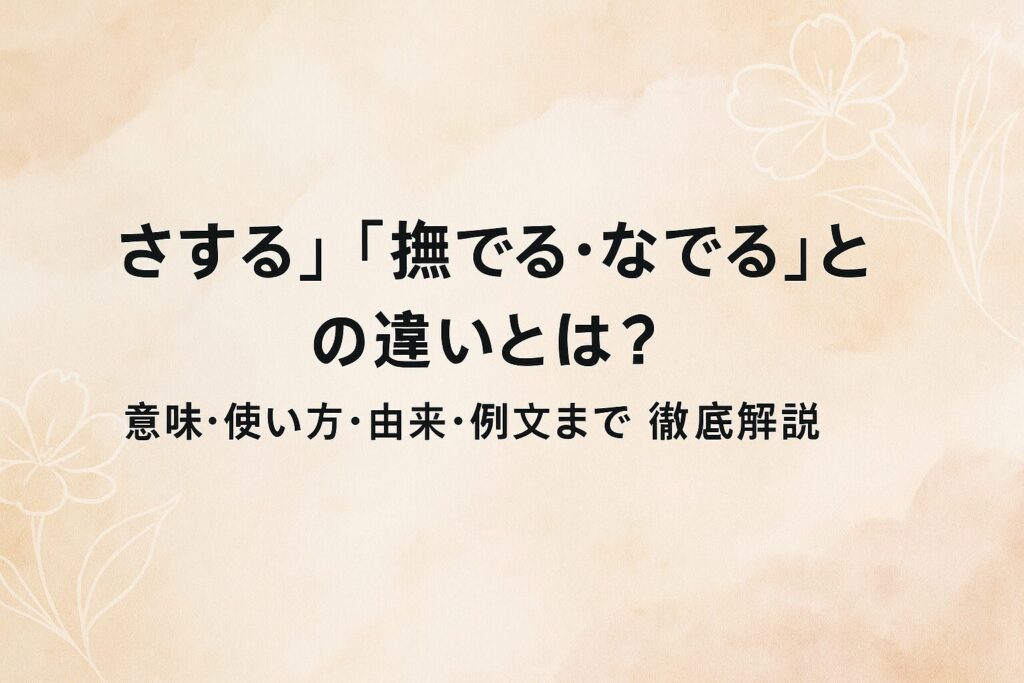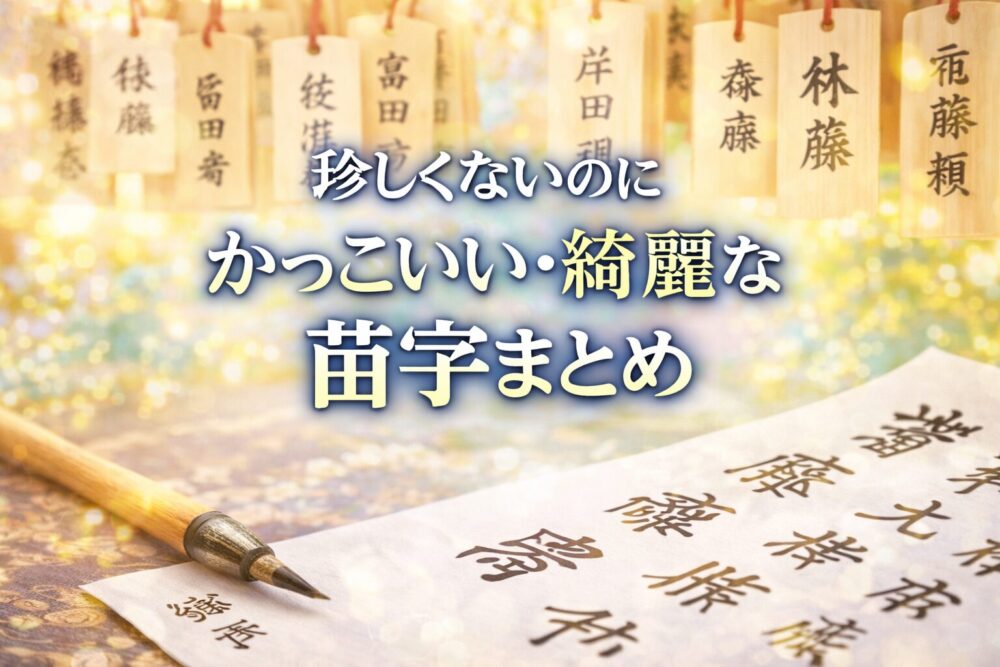日常生活の中で、何気なく使っている「さする」「撫でる」「こする」。
どれも“手を動かす”動作を表していますが、実はそれぞれ少しずつ意味やニュアンスが違います。
この記事では、初心者の方にもわかりやすく、3つの言葉の違いと使い分け方をやさしく解説します。
目次
「さする」の意味・使い方・語源
「さする」は、軽く手を動かして触れる動作を表す言葉です。
日常の中で誰もが無意識に行っている動作でもあり、特に相手を気遣ったり、安心させたりするときによく使われます。
たとえば、子どもが泣いているときに背中をさすってあげると、自然と気持ちが落ち着くものです。
このように「さする」は、単なる手の動きではなく、やさしさや思いやりを伝える心の動作でもあります。
また、体のどこかに痛みを感じたとき、ついその部分をさすってしまうことがありますよね。
これは、手のぬくもりによって痛みを和らげたいという本能的な行動でもあります。
冷えた手をさすったり、疲れた肩を自分でさすったりすると、ほんの少し心が落ち着く気がするのも「さする」が持つ癒しの力のひとつです。
「さする」は人だけでなく、動物や物にも使えます。 たとえば、寒そうにしている猫の背中を軽くさすってあげる場面などにも使われます。
相手に直接触れることで、安心感や信頼を伝える働きがある言葉なのです。
感情のこもった温かい行為を表現したいとき、「さする」はとても日本語らしい柔らかさを感じさせます。
例文: 子どもの背中をさすって安心させる。 冷えた手をさすって温める。 泣き出した友人の肩をやさしくさする。
語源は「擦(さす)る」から来ており、「軽く摩擦する」という意味を持ちます。
古くから「さする」は、単なる摩擦ではなく、心をなだめるように手を動かすという優しい感覚で使われてきました。
そのため、現代でもこの言葉にはどこか温もりと安心感が宿っています。
「撫でる(なでる)」の意味・使い方・語源
「撫でる」は、手のひらでやさしく触れ、愛情や親しみをこめて動かす動作を表す言葉です。
たとえば、かわいい猫の頭をなでたり、子どもの髪をなでてあげたりする場面など、相手へのやさしい気持ちが伝わる動作に使われます。
「なでる」は単に手を動かすだけでなく、相手を思いやる心をそっと届けるような行為でもあります。
日常の中では、なでる行為が安心感や信頼関係を生み出します。
たとえば、ペットをなでるとき、その動きには「かわいいね」「よくがんばったね」といった気持ちが込められています。
母親が子どもの頭をなでて励ますように、「なでる」は言葉よりも深く、温かい感情を伝える手段のひとつです。
また、「なでる」は物理的な動作だけでなく、心理的な癒やしの意味でも使われます。
「心をなでるような言葉」「風が頬をなでる」などの比喩表現では、心を落ち着かせるようなやわらかい感覚を表しています。
このように、「なでる」には身体的な接触を超えて、心の温度を感じさせる豊かな表現力があります。
例文: 犬の頭をなでる。 髪をなでて整える。 子どもの頬をやさしくなでて微笑む。 夕方の風が頬をなでる。
「撫でる」という漢字には「柔らかく触れる」という意味があり、手のひらを通して伝わる温かさを感じさせます。
一方で、ひらがなの「なでる」はより日常的で、柔らかい口調と親しみやすい印象を与えます。
使う場面や相手との距離感によって漢字とひらがなを使い分けることで、より自然で温かな日本語表現になります。
「こする」の意味・使い方・語源
「こする」は、物を押しつけて摩擦させる動作を表します。
たとえば、汚れを落とすときに布でこすったり、眠たい目をこすったりする場面が思い浮かびますね。
「さする」や「なでる」に比べると、力強さがあり、感情よりも物理的な動作に使われる傾向があります。
この言葉は日常の中でとてもよく使われます。
たとえば、掃除のとき「床をこする」「靴をこする」「鍋の焦げをこする」など、何かをきれいにしたいときに自然と出てくる言葉です。
また、目をこすったり、鼻をこすったりといった自分の体に関する動作にも使われます。
無意識のうちに行うことが多く、人間の“触れる”という行為の中でも最も本能的な表現の一つと言えます。
「こする」には、軽く触れる「さする」や、愛情をこめて動かす「なでる」と違って、明確な目的や力の方向性があります。
つまり、「こする」行為には何かを変えたい、取り除きたい、動かしたいという意図が含まれています。
そのため、「汚れを落とす」「熱を起こす」「摩擦で火をつける」などのように、実際的・物理的な場面で多用されます。
例文: 鏡の汚れをこする。 目をこすって涙をぬぐう。 焦げついた鍋を力いっぱいこする。 寒い日に手をこすり合わせて温める。
語源は「擦(こす)る」から来ており、“摩擦する”という意味があります。
「擦る」という行為は、古くから“物に力を加えて変化を起こす”動作として使われてきました。
力を入れすぎると傷つけてしまうこともあるので、「こする」には時に注意が必要な場面もありますが、その反面、努力や根気を象徴する前向きなイメージを持つこともあります。
「さする」「撫でる」「こする」の違いを比較
3つの言葉を比べると、動作の強さや感情の込め方が大きく異なります。
| 言葉 | 動作の強さ | 主な場面 | ニュアンス | 例文 |
|---|---|---|---|---|
| さする | 弱い | 痛み・慰め | 優しくなだめる | 背中をさする |
| 撫でる | 中 | 人・動物 | 愛情・親しみ | 髪をなでる |
| こする | 強い | 掃除・摩擦 | 力を加える | 鏡をこする |
「さする」と「なでる」はどちらもやさしい動作ですが、「さする」は癒やしや慰めのイメージ、「なでる」は愛情や親しみの気持ちが中心です。
一方で「こする」は力を加える行為で、感情よりも実際の動きが重視されます。
使い分けのコツと覚え方
3つの言葉の違いを感覚で覚えるとより理解が深まります。
「さする」は心を癒やすような優しさ、「なでる」は愛情をこめた温かさ、「こする」は力を使って変化を起こす動作を表します。
これらはどれも似たような手の動きを指していますが、そこに込められた“気持ち”が異なります。
言葉を使い分けるときは、その場面でどんな感情を伝えたいのかを意識するとよいでしょう。
また、音の響きにも大切なヒントがあります。
「さ」は柔らかく穏やかな印象を与え、「な」はやさしさとぬくもりを感じさせます。
そして「こ」は力強く、何かを動かしたり変えたりするエネルギーを感じさせる音です。
こうした日本語特有の“音のイメージ”を覚えておくと、言葉の意味を自然に体感できます。
たとえば、子どもが泣いているときは「さする」で安心させ、ペットを可愛がるときは「なでる」で愛情を伝え、汚れを取るときは「こする」で目的を達成します。
状況ごとにこれらを思い浮かべることで、感情と動作を結びつけて自然に使い分けられます。
さらに、イメージトレーニングをすると記憶に残りやすくなります。 目を閉じて「さする」ときの温かい手の感触、「なでる」ときのやさしい動き、「こする」ときの力のこもった摩擦を想像してみましょう。
五感で感じることで、言葉の違いがより鮮明になります。 このように、ただ言葉を暗記するのではなく、場面・感情・音の響きで覚えると、日常の中でスッと自然に使えるようになります。
「さする」と「なでる」の違いをさらに詳しく
共通点:どちらも“優しい動作”です。
どちらも相手を思いやる気持ちがこもっていますが、微妙な違いがあります。
違い: 「さする」=痛みを癒やす、慰めの動作。 「なでる」=愛情や親しみを表す動作。
例: 「背中をなでる」→やや違和感。 「背中をさする」→自然で温かい表現。
「こする」との決定的な違い
「こする」は力を加える物理的な動作を表します。
一方、「さする」「なでる」は感情や思いやりを伴う動作です。
例文比較: ✗「猫をこする」→ 不自然。 ○「猫をなでる」→ 自然。
関連語・類語・派生表現
「摩る(さする)」「擦る(こする)」などの表記ゆれがあります。
また、「撫で下ろす」「擦り付ける」「摩り替える」などの派生語も存在します。
さらに、「触れる」「なぞる」「撫でまわす」などの類似語もありますが、それぞれに微妙なニュアンスの差があります。
たとえば、「触れる」は短い接触、「なぞる」は一定方向に動かす、「撫でまわす」は少し過剰な動きを表します。
外国人に説明するときのポイント(日本語教育視点)
外国の方にこれらの言葉を説明するときは、単に英語訳を伝えるだけでなく、動作にこめられた気持ちや状況の違いを一緒に説明するのが効果的です。
文化や感情のニュアンスまで伝えることで、より深く理解してもらえます。
・「さする」= to rub gently for comfort(やさしく慰める、落ち着かせるように触れる)
・「なでる」= to stroke / pat gently with affection(愛情を込めてなでる、優しく触れて安心を与える)
・「こする」= to rub / scrub with force(力を入れてこする、目的を持って摩擦する)
このように説明すると、英語話者にも「さする」は感情的な癒し、「なでる」は愛情表現、「こする」は物理的行動であると区別しやすくなります。
さらに、ジェスチャーを交えて教えると理解が深まります。
たとえば、「さする」は手を軽く滑らせるような動き、「なでる」はゆっくりとしたリズムでやさしく触れる動き、「こする」はしっかり力を込めて摩擦を起こす動きを実際に見せてあげるとよいでしょう。
また、英語圏では「rub」「stroke」「scrub」などの動詞が使い分けられています。
これらの違いを日本語の感情表現と対応させることで、学習者にとって非常に印象的な説明になります。
たとえば、「rub」は“目的を持って摩擦する”、「stroke」は“愛情をこめて触れる”、「scrub」は“強い力でこする”というニュアンスがあります。
英語との対応を簡単な表にして示すと、より視覚的に理解しやすくなります。
| 日本語 | 英語 | ニュアンス | 主な場面 |
|---|---|---|---|
| さする | rub gently | 慰め・安心させる | 痛み・不安 |
| なでる | stroke / pat | 愛情・親しみ | 人・動物 |
| こする | rub / scrub | 力を加える・掃除など | 物・汚れ |
このように、文化の背景や感情の方向性まで含めて教えると、日本語の魅力がより伝わります。
日本語の感覚を磨くワンポイント
日本語の動作表現は、単なる行動を描写するだけではなく、その背後にある感情や思考をも映し出します。
たとえば「さする」は、相手の痛みや不安をやわらげたいという思いやりの気持ちがこもり、「なでる」は、愛情や親しみを伝えたいという温かい心の表れです。
一方、「こする」は目的をもって力を加える動作で、感情というより“実際の作業”に重きを置いた言葉です。
日本語では、同じ“触れる”という行為でも、手の力加減や心のこもり方によって使い分けが生まれます。
この微妙な違いを感じ取ることができるようになると、あなたの日本語はぐっと豊かで繊細なものになります。
たとえば、「子どもの背中をさする」には慰めの優しさがあり、「犬をなでる」には愛情のぬくもりがあり、「汚れをこする」には行動力や目的意識があります。
また、日本語の魅力はこの“感情と動作の融合”にあります。 どんな動作をどんな気持ちで行うのか――それを言葉で自然に表せるのが日本語の奥深さです。
こうした感覚を意識して言葉を使うと、あなたの話し方や書き方にも、温かみや思いやりが自然と表れるでしょう。
クイズで復習してみよう!
ここまでの内容をしっかり理解できたか、ちょっとしたクイズで確認してみましょう。
単なる知識ではなく、感覚的な違いを思い出しながら答えてみてください。
日常生活の中でどの言葉が自然に聞こえるかを意識するのがポイントです。
次の文ではどの言葉が最も自然でしょうか?
1️⃣ 猫の頭を( )→ この文では、やさしさや愛情が感じられる言葉が合います。
2️⃣ 鏡の汚れを( )→ 力を入れて動かすイメージの言葉がぴったりです。
3️⃣ 子どもの背中を( )→ 相手を安心させたい気持ちを表す言葉が自然です。
ヒント:どの場面にも“手の動き”がありますが、それぞれに込められた感情が違います。
猫にはやさしさ、鏡には目的、子どもには思いやりが必要です。
→ 答え:1. なでる、2. こする、3. さする
さらに応用編として、自分で新しい例文を考えてみましょう。
たとえば、「雪で冷えた手を( )」「お気に入りの布を( )」「眠たい目を( )」など、さまざまな場面を想像しながら言葉を入れてみてください。
動作と気持ちを結びつける練習をすることで、より自然で豊かな日本語表現が身につきます。
まとめ
「さする」は慰め、「撫でる」は愛情、「こする」は摩擦の動作。どれも似ているようで、少しずつ意味が違います。
相手の気持ちや状況に合わせて使い分けることで、あなたの言葉はもっとやさしく、自然になります。